
房総ライフでcoppiが拠点とする富津と南房総。
海の美しさにちょっと差がある気がする。
富津の海は遠浅で、岬は流れが時間帯により速い。

「海藻」「富津」「減少」
この三つの言葉で検索するとAIが以下の回答を出す。

――富津市周辺の海藻場が減少している主な原因は、埋め立てによる浅海域の減少と、磯焼けによる藻類の枯死です。埋め立てにより浅海域が減少し、そこで生育していた海藻(特にアマモ)の生息地が奪われたため、藻場の面積が大幅に減少しました。また、近年では、海藻を食べるウニや魚の増加、水温上昇、化学物質の流入などが原因で、藻類が枯れてしまう「磯焼け」が問題となっています。――
2025年4月19日の夜明け前から富津岬の先端から東側の浜辺を散歩。砂浜に打ち上げられた海藻を観察するにつけ、その少なさに危なさ、焦燥感を覚えた。


「東京湾富津干潟における海藻藻類の長期空間動態」(J-STAGE/保全生態学研究 /10 巻 2005) 2 号/ 書誌)抄録からポイントを引用すると、<航空写真からの目視判定により海草藻場の分布は約70%の精度で判別可能で、海草3種(アマモ、タチアマモ、コアマモ)の識別まではできないが、海草藻場の面積は最大1.79km2(1986年)から最小0.60km2(2001年)まで著しく変動した。分布域は沖側に拡大し、減少する傾向にある。富津沖の水質の変化は小さく、海草藻場の面積変化とは対応しない。開放的性質を持つ富津干潟の海草藻場の空間動態には、埋立てや砂洲の変動などの物理的プロセスが重要な役割を果たしていると考えられる。500m四方で区切った小区画ごとに面積の変動を解析したところ、変動の大きさは各小区画において全体よりも大きいことから、場所ごとに非同期的に増減をすることが、藻場全体の安定的な存続に関与していると考えられる。>

上記の説明では、――富津沖の水質の変化は小さく、海草藻場の面積変化とは対応しないーーとあるが、目に見えない水質の変化があるのではないか。感覚的な意見だが、東京湾出口あたりの海には大量のプラスチックゴミなどが浮遊し、その日の風向きにより三浦半島側、もしくは房総半島側に吹き寄せられるのは事実だ。マイクロレベルの微細なゴミが、温暖化による水温も併せて、海藻の生育に影響を与えていると思う。
1カ月ほど前に、三浦半島の葉山海岸を散策した折、浜辺でワカメを干している現場を見た。こちらの海は太平洋の外海に面し、浜に打ち上げられたワカメや昆布が散見された。生ワカメを拾い、海水で濯いで食してみた。美味しかった。


しかし、富津岬あたりの浜に打ち上げられた海藻は、ゴミの多さから拾い食いする気にはならない。関連して気になるのは、潮干狩りの貝に寄せられた2024年の複数投稿で、「この数年で臭くなった」の記述だ。


潮干狩りの貝、ちゃんと手間をかければ砂抜きはできて、美味しく食べられはする。まずは水洗いし、トレイに重ならないように並べ、塩水につけて暗いところで放置する。(鉄釘もつける=お婆ちゃんの知恵袋)
“磯焼け”とは、藻場が何らかの原因で消失する現象を指す。磯焼けの原因としては、海藻を食べるウニや魚の過剰な繁殖、水温上昇、化学物質の流入、などが挙げられる。海藻はCO2を吸収し、水質の浄化にも貢献する。

富津ではまだ細々とだが江戸前の海苔を養殖しているが、廃業した人も多い。古老の証言、「昭和30年ころまで、この周辺は沖縄のようなきれいな遠浅だった。製鉄業の進出で埋め立てがあって海苔作りは県の指導でやめることになった」2023年6月17日の当ブログ「海苔に捧げた甚兵衛の海」もお読みいただけると幸いです。
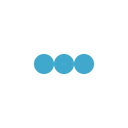
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=20824953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1382%2F9784910511382_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=17104653&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0819%2F9784562050819.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f3aaea8.7730e421.1f3aaea9.ac099214/?me_id=1259747&item_id=15007411&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2020%2F041%2F07458649.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)