
レフェリーに聞く、“スポーツを楽しむ”本当の意味。
日本スポーツ協会の会報、「Sports Japan」03-04月号の第一特集タイトルだ。
スポーツ指導者であり審判員でもあると、意味深だなぁと感じるタイトルだ。

coppiが審判要請講習を受講したとき、<公明:公平>がジャッジメントにいちばん大事と教えられた。これはどんな競技種目でも普遍的なもので、最近はテクノロジーの導入(VARやゴールラインテクノロジーなど)によって、判定の精度が高まり、選手も観客(視聴者)も納得感が増すことが多い。公平で透明性のある判定は基本だ。
記事で興味深かったのは「プロ野球」の<球審は1試合に300球近くのジャッジをしますが、その数と同じだけスクワットをしてボールを見るので足腰がしっかりしていないとできません>の記述。なるほど。それにしても野球審判は、ジャッジの仕草がカッコいいね。

photo©️「Sports Japan」03-04月号
だが、特集を読んでみると「剣道」、「競技かるた」ではちょっとジャッジ事情は異なるようだ。
剣道は、<誤審が明らかだったとしても、勝者も敗者も素直に従うのが剣道のたしなみ>だそうだ。競技かるたは、<最終的には審判が両者の主張を聞き判定するようだが、そこには潔さの文化も漂う>とも。この2つの競技は、タイム判定ではなく、選手同士による勝敗の競い合いで、審判員は<「試合」すなわち「試し合い」を差配する>立場となる。
大相撲をTV観戦すると、力士(選手)の取り組みを行事(主審)が差配する。だが、行事があげた軍配(判定)が、物言い(別審判員の異議申し立て)によりひっくり返るのに、ビデオのリプレイが参考にされることがよくある。
自転車競技でも “写真判定”、競争種目でよく参考にされる。ロードレースでもトラックレースでも何の種目でも、目で見て判別つかないときは写真判定・ビデオのコマ落としリプレイで勝敗をチェックする。それでも勝敗の差配が難しい場合は、勝ち上がり種目なら前段タイムが参考にされることも…。

photo©️「Sports Japan」03-04月号
ロードレースの集団フィニッシュでは、1秒以内は同タイムとみなされ同着になる。密集してフィニッシュラインを通過するときに選手が順位にこだわり足掻いて接触・落車が起きないようにする措置でもある。
安全のためにトラック競技の対戦種目でスターターを務めるとき、審判員はスタート直前に選手に口頭注意で、「今日は特にスプリントに入っての斜行は危険行為として厳しく取ります」のように言い、興奮著しい選手に釘を刺す。
新人選手のタイムトライアルでスタート前、アドバイス的なことを言うこともある。「深呼吸は?」と促す。冷静になってほしいから。

レースの安全管理も審判の仕事の一部だ
酷暑の入門クラスのロードレースではスタート前に、「水を飲んで」とも言う。ホビーレースもルールに則り行われるのは当然だが、勝敗に影響なく、安全を損なわない場合には、ルール運用をそれほど厳格にしないときもある。新米選手にのびのびとスポーツを楽しんでもらい、それで自転車競技普及につながればいいという気持ちがある。
チャンピオンスポーツでは厳格な運用を。入門スポーツではスポーツを楽しむ機会を損なわせず、やる気を削がない運用を。
いいジャッジメント、しなくちゃね。
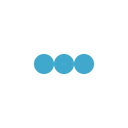
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=20824953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1382%2F9784910511382_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=17104653&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0819%2F9784562050819.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f3aaea8.7730e421.1f3aaea9.ac099214/?me_id=1259747&item_id=15007411&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2020%2F041%2F07458649.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)