
シルクサイクルの荒井正さんから、「棒式変速機の動作を撮影する集まりがある」と聞いてワクワク!
外装変速機の魅力は、動きが可視的なこと。
その典型が“棒式”ではないでしょうか。
4台3タイプの棒式が結集、これは千載一遇のチャンスです。
* * *
当日のラインナップ4つ
2本ロッドの【CAMBIO CORSA】(1933年考案、1935年特許取得: due leve)
1本ロッドの【CAMBIO UN’ASTTICA】(PARIS~RUBEX前1949年製: uno leve)
1本ロッドの【CAMBIO PARIS〜RUBEX】(1949年製品化: uno leve)
そして荒井正氏謹製【シルク・トレーニングピスト】(チェーンステーがスライドするフォーク式変速機。2025年のハンドメイドショーで発表)
<概論>
棒式はパンタグラフ式以前の1940〜50年代の変速機である。シルク・トレーニングピストは古き時代をリスペクトしたモノと言える。その特徴を製作者の荒井氏は、「固定ギヤの変速を外装変速で可能にした。モガキ練習(回転練習)に適切なギヤ比を選択できる」。変速メカは、「スーパーチャンピオンのオスギア。これはスイスの名選手オスカー・エッグ氏の考案で、本来は前ギアの下にチェーンテンショナーが付く」と言う。
3タイプの変速レバーいずれも、トゥーリョ・カンパニョーロによるクイックレリーズと同じで、ローレット状になった指に馴染むレバーを採用。
カンパニューロ・カンビオコルサ登場前に、すでにフランスのスーパーチャンピオン、イタリアのヴィットリアが存在していたが、カンビオコルサはシンプルなメカニズムが利点だ。
<インプレライダー>
変速操作をローラー台上で実演するのは【みかしま じてんしゃ らぼ】主宰・坂田衛さん。ヴィンテージ自転車のロングライドをいつも棒式変速機付きのビアンキFolgorissima(1949年・オリジナルペイント)で華麗に走る達人。しかも彼の棒式はParis-Roubaix 無刻印タイプで、“ウナ・スティカ”と呼ぶそうだ。

カンビオコルサをローラー台に取り付ける坂田氏。手前はCAMBIO工房さん
Check
【CAMBIO CORSA】
カンビオ・コルサには2本のレバーが上下にある。上のレバーはハブ車軸につながっている。下のレバーはチェーンを左右に動かすフォーク(チェーンを左右に移動させる部分:別称「パドル」)につながっている。専用エンドには歯が刻まれ、ハブ軸が一定間隔で移動してチェーンテンションを吸収する仕組みだ。
①上レバーに手を伸ばし、乗りながら操作して後輪の車軸を開放する。レバーは実質的に延長されたクイックレリーズだ。

②ペダルを逆転させながら、下レバーを操作すれば希望のスプロケットに変速できる。

③変速できたらペダル逆転をやめ、上レバーをロック位置に戻す。この操作により後輪車軸はロックされ、フォークの動きも解除される。これで変速操作完了!

坂田氏語る
ペダルを逆転しながら下レバーで変速するが、ローラー台上では慣れないとスムーズに変速できなかった。下レバーはとても軽やかに自由に首を振るからこそ、ちょうどいい(チェーンラインの)位置に収まるのではないか。
coppi語る
実はcoppiも以前に平地で少し操作体験がある。やれば意外に簡単だが、サドルにしっかり座って荷重をかけておかないとうまくできなかった記憶がある。
進化型Check
【CAMBIO UN’ASTTICA】
【CAMBIO PARIS〜RUBEX】
①1本だけのレバーを90度緩めて解除。(1本レバーは「変速チェンジレバー」側面と、クイックレバーの「締め付け&解除」の側面を持つ)

②90度以降はフォークを動かす変速モードになり、ペダリングを逆転してフォークを横方向に動かして変速する。

③ペダルを回転停止状態でレバーを90度戻す。クイック締め付け時にはフォークがロー寄りに動き(チェンジレバーがクイックレバーに替わる瞬間)チェーンの張りを緩める。小さいカム(爪)がエンド側のギザを回して適切なチェーンのタルミを生み出す。これで変速操作完了!

坂田氏語る
1本レバーの操作は考えることなくできる。レバーを緩めて逆転するだけ。レバーを90度ひねった瞬間に変速レバーになる。で、90度戻してチョット緩めて踏みつつ締めればいい。一本レバーは偉大! STIが電動変速になった進化はスゴイっていうけれど、いやいや2本から1本になった進化の方が(インパクトが)凄いです。
気付きPOINT
カンパニョーロのパテントシート(1020-MMT.LTD-1952)の番号で17=クイックシャフト最下部のローレット・ネジを回すことで、6=フォークの位置が微調整できる。1=変速レバーを操作することでフォークが動くわけだが、その動きのきっかけと、変速後のテンション調整(チェーンのタルミ)を調整できている。変速してトップギヤになると8’’のカムが11の歯に噛み合っている。だがローギヤに変速されるとカムは歯から離れている。また。17のローレット・ネジを完全に緩めると8’’のカムは噛み合わなくなる。


坂田氏語る
クイック締め付け時にギザ付き中空シャフトを回転させてチェーンのタルミを調整するのが最下部のローレットです。進化版が逆ネジになっているのにも驚きました。

ローレット・ネジやカム部分(indexing nut)分解写真
画像提供:【みかしま じてんしゃ らぼ】
Check
【シルク・トレーニングピスト】
トレーニングピストはこれをデザイン・製作した荒井さんが変速した。
①変速レバーを操作すると、チェーンステーに直付けされたフォークが横方向にスライドして、3段コグのいずれかにチェーンが動く。ロー側からトップ側に変速することで緩むチェーンテンションは、可動式ボトムブラケットにより吸収されるという特殊な仕組みだ。



荒井氏語る
プーリーがないんですから、とにかくダイレクトです!
coppi語る
すみません、よく理解できませんでした。でも3段コグはフリー機構がない固定歯であり、フォーク機構は直付けであり、さらにロッドである。この3要素から当然、製作者の狙い通りに極めてダイレクトなライド感を了承できます。
<総評>
棒式の変速機は、視覚的な魅力のほか、それを動かすために上体を畳むようにして右腕を変速レバーに伸ばすことが、不便なことでなく、儀式として楽しい。一瞬でスパッと変速する現在のメカと異なり、変速する行為の手練れになることも喜びであり、そのスキルが誇りになる。
犬は撫でると、喜んで飼い主に寄り添い、舐めてくれる。便利な変速機は犬。
猫は撫でたくても、身を翻して逃げて、振り返りじっと見つめたりする。棒式は猫だ。
<蛇足>かつてファウスト・コッピ選手は戦前、レニャーノチームに所属してバルタリのアシストとして走った。兵士として闘い捕虜になり復員した後、戦後はビアンキチームに移籍して活躍した。移籍理由の一端は、ヴィットリアのフォークで変速するメカが嫌で、カンパニューロの変速機の方がお好みだったから、と語り継がれている。それでも1949年のパリ〜ルーベはカンパの2本式の進化版である1本棒式を使って優勝したのでその変速機の名称がCAMBIO PARIS〜RUBEXとなった。
合理主義者のコッピは、きっと犬派だったろう。

撮影会場は埼玉・上福岡のシルクサイクル。手前2台のレニャーノとビアンキは展示販売車両。エロイカやフェッロにすぐに参加して走り出せるコンディション。ビアンキはオリジナル塗装でヴィンテージ的価値高し!!
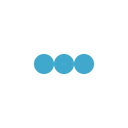
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=20824953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1382%2F9784910511382_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=17104653&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0819%2F9784562050819.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f3aaea8.7730e421.1f3aaea9.ac099214/?me_id=1259747&item_id=15007411&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2020%2F041%2F07458649.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)