
『失われゆく娯楽の図鑑』(グラフィック社/2022年/税別3200円)という本に、「竹馬・けん玉」という項目があった。気になったのが竹馬。

子どもの遊具である竹馬、英語ではbamboo horse。
本には、<竹馬は平安時代に中国から伝わったとされ、当時は竹の先端に馬の頭部、末端に車をつけた春駒が主流だった。室町時代から現在の形に移行>とあり、明治から昭和にかけて男の子に人気の遊びだと紹介。町では見かけなくなったが、伝統的な遊具として金属製の竹馬が、一部の小学校や幼稚園にあるようだ。
中国語で竹馬は「高跷」(読みはゴーチャオ。Gāoqiào)
web検索すると沖縄タイムスの画像として、<島の子たちの通学路は海 竹馬で投稿した小学生1972>があった。

画像引用©️沖縄タイムスより
ちょっと竹馬とは違うけれど、自転車で連想できるのは、「オーバルギヤ」かな。日本ではブリヂストンサイクルが1970年代にジュニアスポーツ車のギミックに採用。シマノの「バイオペース」という製品もあった。クランクを踏み込むトルクがピークに近づく角度で大きなパワーが発揮できるようにギヤが楕円形になっている。最近の記憶では「ROTER Q-RING」があります。竹馬は足の高さ、楕円ギヤは脚のパワーをエクステンションする機材だ。

画像引用©️ROTER ホームページより
さらに連想したのは、パラスポーツの義足。脚を欠損した選手の義足は膝カプラーの下部が弓状のカーボン素材で、まさにそれは「機材」そのもの。
実用的な竹馬的な機材を楽天市場で見つけた。軽量アルミニウム合金性の「高性能乾式壁支柱」は、固定ストラップで脚に固定して、フット長さはウイングナットで調整可能。壁塗りや清掃作業の高所作業に用いる「機材」だ。

画像引用©️価格.comより
江戸時代に日本に滞在したイギリス人女性は、路上で見た竹馬を、「竹製の乗り物に乗った少年を見た」と見聞録(Child-life in japan)に記した。その乗り物は「SAGIASHI(鷺足)」で、竹の棒に横木を止めてそこに足を乗せて歩くと説明した。

「1861年、子どもを竹馬に乗せたアメリカ人女人」
画像引用©️webより

上の画像では子どもが竹馬の棒を背後に持って操作している。日本人は棒を前にして操作する。その差異を、『江戸のスポーツ歴史辞典』(谷釜尋徳著/柏書房/2020年/税別2000円)では、<日本人は右足(左足)が前進すると右(左)が前に出るようなナンバと呼ばれる身体文化を持っていて、半身の連続で歩く竹馬の技法をそれほど違和感はなかった。一方、ヨーロッパ文化は半身姿勢の発想が薄かった>と説明している。
祭りや伝統芸能で、竹馬のような脚を伸ばすデバイスを利用する事例はたくさんある。
サーカスのピエロも、脚を伸ばす仕掛けで観衆を感心させるし、大道芸でも足長芸がある。

ところで数年前、久しぶりに竹馬に挑戦する機会があった。
子どものころは自分の背丈の倍ほど高い竹馬を操れたのに低い竹馬しか乗れない。
機材を操るにはやっぱり、慣れと精進が大事ですね。
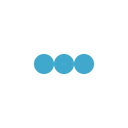
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=20824953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1382%2F9784910511382_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=17104653&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0819%2F9784562050819.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f3aaea8.7730e421.1f3aaea9.ac099214/?me_id=1259747&item_id=15007411&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2020%2F041%2F07458649.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)