
「片倉と聞いていますけどね…」
ビンテージ自転車専門店の葉山自転車市場で、天井の梁にぶら下がっていたのがこれ。
「横浜にあった野口商会の先代が乗っていらしたフレームですが…、よく分からない」との由。お預かりして持ち帰った。

改めて観察。片倉シルク号であれば、フレームに≪メルボルン、ローマ、東京、メキシコ、オリンピック連続出場車≫の小さなステッカーが貼られていたものだが、このフレームにはない。唯一ダウンチューブには、昭和41年(1966年)のサイクリングラリー参加記念ステッカーだけが残されている。

片倉自転車の創業は1946年(昭和21年)で、そのルーツは1872年(明治5年)に官営模範工場として設立された富岡製糸場の流れにあった片倉工業富岡工場であり、全国にあった製糸工場のひとつが東京・福生にあった森田製糸工場㋲。それが1929年(昭和4年)に製糸を中止して第二次大戦中は立川飛行機に関連する軍需工場になった。
敗戦で平和産業転換を目指して森田製糸工場㋲は片倉工業多摩製作所と改称して前述のように1946年に自転車製造を始め、その自転車が1956年のオリンピック・メルボルン大会、1950年のローマ大会、1964年の東京大会、1968年のメキシコ大会に使われたということになる。
オリンピック連続出場と並んで記憶に残るのが、≪低温溶接≫のアピール。
<オリンピックで大活躍したイタリアCHINLLIは世界中の国から依頼を受けた、日本も多くのCHINLLIを購入した、タンデムは日本選手の体格に合う物は供給されなかった、数社が製作したが最終的にシルク号が本番でも使われた。これは低温溶接法による強度の実証となった。>と絹自転車のブログに記されている。

このブログは、片倉自転車のレーサー部門でトーチを握りフレームを作っていた荒井正氏による。そこで、このフレームの写真をメールで送り確認してもらったが返答は「片倉ではありません」だった。「アメリカ製ではないですか」とも書かれていた。
そこでフレーム製作の権威、梶原利夫氏にご教示を求めた。
結論:片倉のフレームという可能性はある。
(梶原氏談)
内側にラグがインサートされているラグレスフレームで、アメリカ風の作りですね。
溶接は低温溶接だと思われます。塗装を剥がせばロー材が見えるので検証できます。
ハンガー部もアメリカ式で、BBは宮田工業製造の米式です。左にネジが見えていて球押し式です。右は打ち込み式です。ハンガーもシートチューブが後退した米式。フレームチューブは25.4でインチ規格(ダウンチューブで計測)。

↑BBシャフトの奥側にネジと溝がある特徴的な宮田の米式BB


↑ピアスのフレーム。エンドは調査フレームのエンドと同一形状
そもそも片倉は低温溶接のラグレスを看板にしていたけれど、戦後すぐ昭和21年ごろにフレーム製作を開始した当時はラグ付きだった。
低温溶接の技法はスイスのワッカーマン氏が1936年に発明し、アメリカで実用化された。アメリカの溶接業者が昭和23年(1948年)に日本の溶接学会に低温溶接を紹介してセールスした。
片倉がラグレスになったのは昭和24年以降ではないか。また、昭和25年以前は日本の主だった自転車製造者にヨーロッパ風の製造知識がないので、アメリカの製造知識でフレームを作っていた。
このフレームは、アメリカのピアスを模倣している。BBは宮田の米式だ。よって昭和25年以前に製造されたピアス模倣の日本製である。より詳しく検証するにはフレームを切断して内ラグであることも確認するといい。

↑1920年の米国鉄製品カタログ「THE IRON ACE CATALOGUE」(梶原利夫氏蔵書)より、自転車フォーク肩(右側)

↑1920年の米国鉄製品カタログ「THE IRON ACE CATALOGUE」より、自転車ラグ

↑調査フレームのフォーク肩は、「THE IRON ACE CATALOGUE」自転車フォーク肩(右側)と同じと思われる
ビンテージ自転車では独自の歴史があるアメリカ。
1893年に世界初の自転車世界選手権(トラック種目)がシカゴで開催された。エロイカの審査ではエロイカ世界基準は1987年以前で共通だが、それ以前の古い年代は1930年が基準。だがアメリカは1949年にしている。理由は東海岸で6日間レースが盛んだったアメリカならではのブランドがあるからだ。
ピアス号を彷彿とさせるこのフレーム、第二次対戦後に日本で製造されたことは間違いない。
Special Thanks(五十音順):荒井正氏、梶原利夫氏。
参考文献
絹自転車製作所「絹歴史」
https://www.silkcycle.com/history/katakura-silk.html
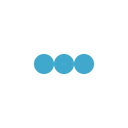
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=20824953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1382%2F9784910511382_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=17104653&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0819%2F9784562050819.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f3aaea8.7730e421.1f3aaea9.ac099214/?me_id=1259747&item_id=15007411&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2020%2F041%2F07458649.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)