
日曜の早朝5時、ハンドルを地元の神社に向けた。
道路脇にずらっと、たたんだ屋台が静かに並ぶ。

そういえば前日、祭り太鼓が微かに聞こえていたな。
ここ数日、祭りの幟がそこかしこに掲げられていた。
そう、今日は地元の秋祭り、子ども時代は特別な娯楽だった。
東京・豊島区の“長崎神社大祭”における屋台と里神楽をご紹介します。

長崎神社は、西武池袋線・椎名町駅前にある。
椎名町といえば漫画ファンにはトキワ荘アパートで知られていますが、長崎神社は創建年代不明で、明治初期の廃仏毀釈により金剛院(まんが地蔵あり)から切り離され旧:十羅刹女社が、長崎神社に改称された。

境内井戸の傍らにある水鉢、<奉納十羅刹女社 享保一八年>と文字が刻まれている
境内には大きなイチョウや椎の木があり、神楽殿がある。
笛や太鼓のお囃子は子ども時代からこの神社でよく聞いてものでカラダに染み込んでいる。郷土芸能、いいものです。



日曜は午後、1時間毎に夜9時まで3人の演者が笛と太鼓で、神々の祝福と五穀豊穣の祈りを奏でた。また、大黒天に扮した踊り手が打ち出の小槌を盛大に振ってくれたのですが、若い世代の関心は薄かった。さみしい。
とても素晴らしい伝統芸能、ぜひみなさん来年、観てください!!
武州里神楽・石山社中が率いる楽師と舞手が登場。観覧無料!
結局、早朝に屋台を目撃、昼間の里神楽を観て、地元の神輿につきあい、里神楽最終ステージまで日がな一日祭り三昧。おもしろかった。
屋台はカウントしたら121も並んでいた。
朝9時には働き手らが現れ、1時間ほどで色とりどりの簡易看板がずらりセットアップ。食べ物の匂いが漂う。
高齢の痩せた男性が仕切っているようで、段取りや不慣れな若手にアドバイスを与えながら足早に動いていた。働き手の1/3ほどは黒いTシャツの若い衆、女性は総じて化粧濃い目。でも、伝統的な“お面売り”などは高齢御夫婦も見かけました。






121の屋台、分布は以下のとおり。
祭りエリアをcoppi的に分類。A境内エリア(26屋台)、B神社脇道路エリア(40屋台)、C椎名町駅前エリア(34屋台)、D商店街延長道エリア(21屋台)。合計121屋台。
祭り来場者の年代層は幅広い。親子、少年・少女、青年、カップル、熟年夫婦。外国人もかなりいる。ほとんどは単独ではなく、誰かと歩いていた。
長崎神社の氏子地域は、主に豊島区の長崎、南長崎、千早、要町、高松、千川、そして目白、西池袋、池袋の一部地域とかなり広域。来場者の動線はまちまちだが、参拝を伴う人らは最終的にAエリアに来る。
境内AエリアとB神社脇道路エリアには、居酒屋スペースが設けられ、ゴミ回収の配慮もあった。食べ歩きも楽しいですがね〜。
昭和の子ども時代はバナナの叩き売りなど、テキヤや香具師の愉快な口上を聞けた。でも、フーテンの寅さんはもういない。
売人と客のやりとりは露天や屋台のおもしろさだ。 “チョコばなな”屋台では売り子とジャンケンをして客が勝てば本数が増える“勝負コミュニケーション”がある。子ども心はドキドキです。
“金魚すくい”、“スーパーボールすくい”、“宝石すくい”、“キャラクターすくい”など、すくい系にも勝負コミュニケーションの楽しさがある。

ジャンケンのルール。一種のバクチだよね!

昔ながらのスマートボールも人気が高い
いずれのエリアにも配置されるのが、「やきそば」、「から揚げ」、「お好み焼き」、「じゃがバター」。不動のメニューだ。定番は、綿飴(色違いあり)、フルーツ水飴、りんご飴。


焼きそばなどの人気屋台の1日の売り上げ高、凄いよ!
「串焼き」、「ベビーカステラ」はブランド性付与がお約束。カステラは〜堂、串焼きの和牛系は地名(佐賀牛、神戸牛)が付き、同じ商品を扱うにも巧みに名称で権威づけ、味付けやフレーバーで嗜好に応じての差別化を図っている。
異国系の筆頭は伸びるトルコアイス、ドネルケバブ。他に目新しかったのが、タイラーメン、台湾のソウルフードである餡餅(シャーピン)。
祭りはハレの日。だから子どもは特別にお小遣いをもらえることもある。誰もがウキウキ楽しみたい気分。屋台の原色看板、美味しそうな匂い、ほろ酔いの人がいて当たり前。昔も今も、夜祭は子どもが覗ける歓楽街。


町会の御神酒処で1000円奉納!
長崎神社大祭、ヨサコイ踊りやサンバカーニバルはない、じつに正統派の秋祭り。
誇りに思う。
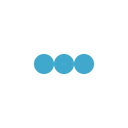
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=20824953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1382%2F9784910511382_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=17104653&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0819%2F9784562050819.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f3aaea8.7730e421.1f3aaea9.ac099214/?me_id=1259747&item_id=15007411&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2020%2F041%2F07458649.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)