
日本のオーダーメイド自転車について、7月初旬から少しずつ再チェックする作業を始めました。鳥山新一さんが提唱したスポーツサイクルの文化、オーダーメイド自転車の黄金期は遙かなる影になりつつある? いえいえ、違います。

昭和の時代、ハンドメイドはスチール素材の溶接フレームでした。


その常識が変わっていった。ヨーロッパのロードレースに登場した「ALAN」は1970年代前半にイタリアで誕生。アルミニウムのチューブをラグでつないだ接着工法。その後、カーボンを前三角に採用した自転車も登場し、1990年代はカーボンやアルミニウムがスポーツ自転車の“新素材”と言われた。
接着工法のフレームは1980年代、アマンダの千葉洋三さん、千葉さんに学んだ松永かずはるさんが手掛けています。

photo●蟹由香
アルミのフレームが当たり前になったのは、1980年代のマウンテンバイク台頭。Tig溶接で作るアルミのロードバイクが定着したのは、台湾のGIANTが1990年代後半に市販したスローピングフレーム。その手法をいち早く取り入れたのは大阪にあったビチクレッタノコ(委託生産)で、そのフレーム形状は「コンパクトフレーム」と呼ばれました。
伝統的ハンドメイドのマニアからすると、前上がりのフレームで剛性アップを図ったスローピング形状は当初、違和感があると嫌われたものです。
でも、小さな三角を作って剛性アップの考え方は、キャンピング社のフレームでも以前からやっていたのですね。
21世紀のハンドメイド世界観は、NARBS(North American Handmade Bicycle Show)のインパクトが大きい。伝統的なフランスやイタリアやイギリスのスポーツ自転車とNARBSに出展される作品群、その差異にcoppiは “アメリカ的コンプレックス”を感じた。
NARBSに出展されたロードバイク群を見ると、そこに伝統的なイタリアンバイクへの憧憬が滲み出ていた。それが「コンプレックス」と映った。しかし、回を重ねるとNARBSに出展される作品群が自由すぎるほどで、「天衣無縫」と称すべきに考えを変えた。
ケルビム二代目の今野真一さんは、2009年に初めてNAHBSに出展し、2つの賞を受賞しました。2012年には、曲線美を追求した “ハミングバード”で最高峰の賞である「Best of Show」と「プレジデンツチョイス賞」をダブル受賞。NARBSにはアトリエ キノピオの安田正夫も木製自転車 “Kinopio”を出品した。

ニューウエーブのビルダーたちに注目したい。
NARBSに刺激を受けてビルダーになった愛知・丹羽のSim Works服部晋也さん、彼の工房で経験を積んで兵庫・姫路自らのAYA BIKESを興した女性ビルダーの赤松綾さん。赤松も学んだ東京サイクルデザイン専門学校の一期生で滋賀・甲賀でmacchi cyclesを営む植田真貴さん。

ここ数年、アマチュアのビルダーが自分だけのために自作自転車を手掛けている。それも、多様な素材で、多様な手法で、マジに走って愉しんでいらっしゃる。
コロナ禍後に、地方の小規模ショップがフレーム作りに着手して「地元のサイクリストに向き合い“地産地消”の自転車を作ります」(西沢豪さん:和歌山・新宮WHEEL ACTION店主)という流れもある。兵庫・三田の古民家自転車工房エコーでモノづくりする唯陸奥男さんもいる。
ハンドメイド自転車の火は、途切れることなくチロチロ明るく燃え続けています。
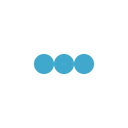
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=20824953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1382%2F9784910511382_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=17104653&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0819%2F9784562050819.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f3aaea8.7730e421.1f3aaea9.ac099214/?me_id=1259747&item_id=15007411&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2020%2F041%2F07458649.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)