
雲が風に流され、光が映ろう、その変化を眺めるのが好きです。
11月1日〜2日に開催するFERRO e Mari Montiで、セミナーを1枠担当する。
セミナーは1時間弱で、聴講定員20〜30人程度。鋸山美術館の敷地内にある古い蔵でやる。

表題は「オーダーブランドAtoZ」で、オーダーメイド自転車のヘッドバッジ=ブランドにまつわる与太話。その準備で3ヶ月前からテキスト執筆して小冊子にまとめ、パワーポイントも用意。今日は会場の蔵に出向いてパワーポイント動作確認。



石橋は叩いて渡る。動作確認を試みるにパソコン、プロジェクターとも機種を差し替えながら苦節1時間(短い?)、安心して本番を迎えられるようになった。
セミナーのキモは、1961年の記録ニュース映画(10分)『東京―大阪ツーリストトロフィー』だ。
前半は自転車が江戸末期から明治初期に日本上陸し、日本の職人がコピーし、やがて自転車産業が誕生するのと並行して、自転車で遊ぶ人たちが出てきた。不忍池で大規模な自転車レースが行われた。ま、駆け足自転車史です。
で、『東京―大阪ツーリストトロフィー』を挟んで本題のヘッドバッジになる。
1961年のニュース映画に登場する道路競争用自転車のまあレトロ感、驚きです。
その3年後、1964年の東京オリンピックには、ヨーロッパ並のロードレーサー(チネリのような)が国産化され、その数年後にはロードマンがブリヂストンから販売。1960年代は国産スポーツ車の著しい進化があった。
さらに日本のオーダーメイド自転車文化は1970年〜2010年ほどの期間に花開き、やがてフェードアウト方向に鎮静したが、どっこい部分的に息を吹き返しつつある。ま、そんな与太話をします。今回のセミナー準備で改めて感じたのが競輪=NJS制度が果たしているハンドメイド自転車文化の下支え経済効果。また、オーダーメイド自転車の隆盛は自転車専門誌の相次ぐ創刊ラッシュから廃刊に至る栄華衰退と見事にリンクしていること。


満ちては欠ける月、雲に遮られる陽光みたいでおもしろい。

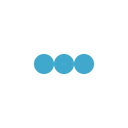
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=20824953&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F1382%2F9784910511382_1_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1a7b0555.ed2293c7.1a7b0556.cc8c886f/?me_id=1213310&item_id=17104653&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0819%2F9784562050819.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1f3aaea8.7730e421.1f3aaea9.ac099214/?me_id=1259747&item_id=15007411&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdorama%2Fcabinet%2Fbkimg%2F2020%2F041%2F07458649.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)